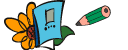| 山野草日記 - 最新エントリ |

 最新エントリ配信
最新エントリ配信 |
最新エントリ
2006/05/12
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (7:13 pm)
|
5月13日、14日「秋保大滝植物園まつり」というのがあるそうです。(秋保町馬場字大滝) お天気が心配ですが、大國神社山野草公園とともにハシゴなさってはいかが。 秋保大滝植物園→http://www.sendai-park.or.jp/web/guide/info_akiu.html |
2006/05/11
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (12:34 pm)
|
花が終わり葉も枯れ始めたとはいえ、まだまだ頑張っているのが大小さまざまな1枚葉のカタクリたちです。 数ミリのものから10センチ以上に達したものまで、ときにはすっぽりとマルバダケブキの陰になりながらも、それぞれの環境でお日様の恵みを受けています。 そんな姿を見るのも案外楽しい今日この頃です。 今日は写生会グループ10数名の方が、風景画を楽しんでいかれました。 季節感を楽しむと言えば俳句の会の皆さんもいらっしゃいます。 |
2006/05/10
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:40 pm)
|
昨年境内地に移植した2本のサイカチの木です、青々としていてほっとしました。 霜害が懸念され根元に厚めの土饅頭をこさえておきましたが、どうやら無事に越冬できた様子です。 どこまで大きくなるか楽しみです。 |
2006/05/10
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:09 pm)
|
至るところにヤマジノホトトギスの花芽が出てきています。 花期は8月〜9月頃なので成長をじっくり観察できそうです。 花暦⇒https://sanyasou.info/doc/hana/yamagino.html |
2006/05/09
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:25 pm)
|
既に枯れてしまったカタクリの葉が目立つようになってきました。 間伐作業後、初めて迎えた早春季をどのように過ごしたのでしょう。 さび菌感染の影響は気がかりですが、来春が待ち遠しいです。 |
2006/05/09
2006/05/08
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:08 pm)
|
*画像公開終了 マルバダケブキのつぼみが増えてきています。 マイヅルソウの花も咲き始めています。 茎のまだら模様からすると、ホソバテンナンショウではないかと。 大きくなるにつれ性が変わるとされているようです。 |
2006/05/08
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:03 pm)
|
この春よりカタクリ観察のため、杜の小径に4つ谷間に4つ、計8つのメッシュ枠を設けてみました。 場所によってはマルバダケブキによって覆われる面積が全体の3分の2以上になろうか、というケースも出てきました。 しかし、そこはカタクリ。争う前に地上での生活をほぼ終えています。 カタクリの実であるさく果が地中の鱗茎から送られた養分で次第に膨らみ、やがて3つの部屋が形成されてきました。 種子は6〜8ミリ程度になり、熟して部屋が裂開していくにつれ甘い匂いを放つそうです。 大小さまざまなアリたちの動きも活発になってきているように見えます。 生産された種子のうち生き残って実生になるのはその10分の1に満たない、という資料もありますから、厳しい生存競争が待っているのですね。 |
2006/05/07
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:13 pm)
|
霧に包まれた杜の小径に入りました。 今シーズン開花第一号のカタクリの家である切株の周辺は、今ですとチゴユリの群生などが見られます。 しかも花を2つつけたものが他の場所より多く、たわわに咲いているのです。 よほど栄養状態や生活環境が安定していて住み易い場所なのでしょう。 ものの本によると、チゴユリは「移動」する植物なのだそうです。 栄養繁殖・・ショウジョウバカマを調べていて知った言葉がまた出てきました。 チゴユリの場合は地下でランナー(走出枝)をのばし、やがて親から切れて個体が独立、繁殖していくようです。 栄養の配分は、種子よりも栄養繁殖体のほうにより多くの栄養を送り込んでいる、という分析もあるようです。 |
2006/05/06
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (1:22 pm)
|
旧暦ですと5月への月変わりです。 この日から立秋の前日までが夏とか。 春分と夏至の中間にあたります。 ハグマの仲間でも昨秋、最後に花をつけたのがオヤリハグマでした。 開花を待ちわびて何度も足を運んだものです。 花が枯れると白い筆先のような毛が残りました。 これを仏具の払子(ほっす)に見立てたとか。 花暦⇒https://sanyasou.info/doc/hana/oyarihaguma.html |