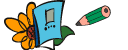| 山野草日記 - sanyasouさんのエントリ |

 sanyasouさんのエントリ配信
sanyasouさんのエントリ配信 |
最新エントリ
2006/04/29
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (7:20 pm)
|
道端にたった一輪だけ咲きかけのヒメシャガ。 秋口にも時期はずれの開花を確認しました。不思議な花です。 不思議と言えば見学者からよく聞かれるのがこれ、産毛の生えたヤブレガサです。 |
2006/04/27
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:14 pm)
|
整備中の区画を含めた山野草公園全体からすれば、いわば“カタクリの早咲きエリア”ともいえる「杜の小径」ではその多くのカタクリが結実の時期を迎えています。 イワウチワやショウジョウバカマもそろそろ花期を終えてきています事をご了承ください。 今朝の新聞折込み記事によって、これからが見頃と言う印象を与えてしまったとしたら・・・・お詫びしないといけないですね。私を含めたスタッフにとっては全てが初めての経験なのです。 ヒトリシズカが展開してきました。 日々・・まるで役者が入れ替わるように新たな発見があるのも事実です。 |
2006/04/26
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:07 pm)
|
山野草公園入口手前の休憩所に鉢植えコーナーが設けてあります。 これは散策路の真中に出てきたカタクリを始めセリバオウレン(写真)などを杜に入れない方にも見て頂けるように、という趣旨で移植したものです。 さすがに杜の中と違う環境で元気はありませんが、セリバオウレンの風車やカタクリのさく果がご覧になれます。 |
2006/04/26
2006/04/25
2006/04/25
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:20 pm)
|
カタクリについて多数のお問い合わせを頂戴しています。 花が終わってさく果となった個体も大分目に付くようになってきました。 イワウチワもほぼ花を落とし・・残った赤い部分が目立ってきています。 入れ替わるように、チゴユリやマイヅルソウ、ヒトリシズカ、フタリシズカ・・・ 私の頭では到底整理がつかないくらい・・続々と、春を謳歌する小さき者たちが姿を現しています。 |
2006/04/24
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (3:59 pm)
|
来年公開予定の8つほど連なる谷では、現在公開中の杜の小径に比べてカタクリ、ショウジョウバカマ、イワウチワなどの開花時期が少し遅くなる傾向があります。 地山を覆い隠す枯葉のぶ厚い層の下はたっぷり水が蓄えられていて、足がめり込むほどです。 辺縁部に沢が流れる湿潤な土地柄に、通年で吹くのでしょうか冷涼にして力強い風・・それらが特有の生育環境を作り出しているようです。 ショウジョウバカマとカタクリたち。マイヅルソウも仲間入り。 |
2006/04/23
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:08 pm)
|
今日は杜の小径のメッシュ観察日。 いつものように野帳に記録をとっていたところ、一部のカタクリの葉の表面に黄土色の何かが付いているのを見つけました。 どうやら、カタクリの葉に寄生して生育を阻害するといわれる「カタクリさび菌」の仕業のようです。 感染範囲はまだ小さいようですが、葉の裏側から表側にまで侵食しているように見えます。 どのように対処したらよいのか調べてみようと思います。 さび菌についての情報をお寄せいただけると幸いです。 引用: NewtonSpecialissueより:カタクリさび菌は分類学的にはキノコ類に近いカビの一種で、カタクリの葉に寄生してさび病を起こす。 |
2006/04/22
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (5:29 pm)
|
昨年の初夏の頃お声掛けをいただき山野草の森づくり活動に加わり・・気が付いたらそのまま居付いてしまいました。 春になってこんな風景が広がったらなぁ〜、という漠然としたイメージを想い描いていました。 ふかふかとした春の温かい風が吹く野原一面を埋め尽くすカタクリ。 それが、今まさに目の前に広がっているなんて。 なんだか不思議です。 |
2006/04/21
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (6:12 pm)
|
全身に産毛を生やし花芽を鈴なりにしてくるまっていたイカリソウが開花しました。 実物は初めてなのですが、なるほど独特の形をしていますね。 花暦⇒https://sanyasou.info/doc/hana/ikari.html 独特といえば金色に輝くトリアシショウマもその名の通りの格好です。 モミジハグマも出てきました。包まった葉を広げてみると確かにモミジのような形をしています。 これがああなるなんて・・成長した姿からは想像もつきませんでした。 |