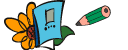| 山野草日記 - 最新エントリ |

 最新エントリ配信
最新エントリ配信 |
最新エントリ
2008/03/27
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (5:50 pm)
|
 看板の手直しにと、夕暮れの第1群生地に入り込みました。 数株の開花を確認しましたが、気温が下がり既にどの花も閉じていました。 森全体はまだモノトーンなのに、薄暮の林床のそこだけが薄紫色が映えて印象深いものでした。 |
2008/03/27
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (5:37 pm)
|
 タカさんの指揮による、新たなツリーハウス作りが進行中の冒険広場。  製材した残りの「木の皮」を貼り付け側壁が出来てくると、ぐっと雰囲気が出てきました。  |
2008/03/24
2008/03/24
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (4:56 pm)
|
 第1群生地内にあるメッシュの現在の様子。 第1群生地内にあるメッシュの現在の様子。 昨シーズン、開花したカタクリに付けた標札(1)の傍から、さらに複数の有性個体が現れているのが分かります。 昨春までは一枚葉の姿で地上生活を送り光合成を行って、晴れて有性段階に達したようです。 これらのカタクリ、これから花開くまで上方に伸びたとしてもミニチュアサイズに留まると思われ、専門家をして「親子」カタクリの「子」のほうではないでしょうか。 一般に7〜10年ともいわれる開花までの年月を早足で駆け抜け、短期間で花をつけるに至ったのかもしれません。 |
2008/03/22
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (5:24 pm)
|
温暖化の影響なのでしょうか、やはり開花の時期は例年より少し早目のようです。 特にイワウチワは、例年より早くご覧になれそうですよ。 2つの群生地入り口のゲートに「冬季休園中」と表示していたロープを外し、入園できるようになりました。 ところどころで傷んだ手すりの修復作業などを行っている最中で、多少うるさいかもしれませんがご容赦ください。 冒険広場でも、タカさんが新たなツリーハウス作りに励んで下さっています。 まだ製作途中で危険ですから、くれぐれも近付かないでくださいね! |
2008/03/20
2008/03/20
2008/03/20
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (6:00 pm)
|
 ここ数日の陽気に刺激されたのか、イワウチワの中にはもうすぐ花を開かんとしている個体も出てきました。 公園日誌を見ると、過去2年連続で3月27日にシーズン開花第一号を確認しています。  一方、カタクリもうっすらと紅を差したように色付くつぼみがちらほら見られるようになっています。 |
2008/03/18
|
カテゴリ: 山野草日記 :
執筆者: sanyasou (11:36 am)
|
 ここがツリーハウスへの上がり口になるのでしょう、丸太を組み合わせたらせん階段が出来てきました。 垂木を格子にしたテラスも形になってきています。 この上にテントを張ったら、星を見ながら一夜を過ごせそう。  |
2008/03/17